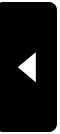2014年06月25日19:23

この間から引き続き…
相変わらず、家にこもってチクチク創作活動が続いております。
というか、既に7月のお祭りまで1ヶ月を切ってきたので、追い込み状態
今回、装束の差しは遠州綿紬で統一したいと思っていて…
花火には欠かせない「手甲(てっこう)」を作りました。
遠州綿紬を使って、お祭りで使う「手甲(てっこう)」を作ってみた

この間から引き続き…
相変わらず、家にこもってチクチク創作活動が続いております。
というか、既に7月のお祭りまで1ヶ月を切ってきたので、追い込み状態

今回、装束の差しは遠州綿紬で統一したいと思っていて…
花火には欠かせない「手甲(てっこう)」を作りました。
元々手甲というと、手の甲から腕を覆うものが多いのですが、お祭りで使われる手甲は手首から10~15cmくらいのもの。
「手筒」とも呼ばれるそうで、また、大工や鳶、庭師などの職人がはめて外傷から身を守るために付けていたとのことです。
腹掛けなんかも元々大工さんの作業着が由来ですし、納得。

という訳で作ってみましたが。
今回は直線裁ちだけではうまくできないので、最初に新聞紙でカンタンな型紙から作ってみました。
新聞紙で作る利点は
・紙代がかからない
・セロハンテープやマスキングテープなどで仮止めして、実際に身に着けた時の様子が分かる
・失敗してもまたすぐに作れる
所かなぁと。
色が薄い布を使う時には、新聞紙のインクが写らないような注意は必要ですが…
今回は簡単に大きさを合わせた後、型紙を半分に切りました。
これは曲線を左右対称に書ける自信がなかったので、布を輪にして半分だけ書きました。

後は、切って縫って、返してまた縫ったら完成です。
1枚だけだとちょっと寂しかったので、裏表違う布をあわせて、作りました。
今回は簡単にマジックテープとスナップボタンをつける予定なのですが…
遠州綿紬は洗うと縮みやすいので、一度水洗いをしてから最終的に位置を決めて留めます。
布にもよりますが、この縮みは仕方がないもの。
どのくらい縮むかなどは、布を買う時にお店の人に聞けば、目安を教えてくれます。
布の水通しなども最初は分かりづらかったのですが…
最近何度か繰り返している内に、なんとなくやり方のコツなども分かってきて、楽しくなってきました♪
いろんなハンドメイド作家さんに「ミシンは数をこなすのみ!」と言われていた感覚も、やっとわかってきたカンジ…。
カンを忘れない内に、次に何を作るか、早目に決めようっと♪
「手筒」とも呼ばれるそうで、また、大工や鳶、庭師などの職人がはめて外傷から身を守るために付けていたとのことです。
腹掛けなんかも元々大工さんの作業着が由来ですし、納得。

という訳で作ってみましたが。
今回は直線裁ちだけではうまくできないので、最初に新聞紙でカンタンな型紙から作ってみました。
新聞紙で作る利点は
・紙代がかからない
・セロハンテープやマスキングテープなどで仮止めして、実際に身に着けた時の様子が分かる
・失敗してもまたすぐに作れる
所かなぁと。
色が薄い布を使う時には、新聞紙のインクが写らないような注意は必要ですが…

今回は簡単に大きさを合わせた後、型紙を半分に切りました。
これは曲線を左右対称に書ける自信がなかったので、布を輪にして半分だけ書きました。

後は、切って縫って、返してまた縫ったら完成です。
1枚だけだとちょっと寂しかったので、裏表違う布をあわせて、作りました。
今回は簡単にマジックテープとスナップボタンをつける予定なのですが…
遠州綿紬は洗うと縮みやすいので、一度水洗いをしてから最終的に位置を決めて留めます。
布にもよりますが、この縮みは仕方がないもの。
どのくらい縮むかなどは、布を買う時にお店の人に聞けば、目安を教えてくれます。
布の水通しなども最初は分かりづらかったのですが…
最近何度か繰り返している内に、なんとなくやり方のコツなども分かってきて、楽しくなってきました♪
いろんなハンドメイド作家さんに「ミシンは数をこなすのみ!」と言われていた感覚も、やっとわかってきたカンジ…。
カンを忘れない内に、次に何を作るか、早目に決めようっと♪